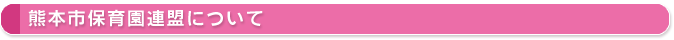 
|
Copyright © KUMAMOTOSHI HOIKUEN All right reserved.
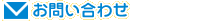 |
| 一般社団法人 熊本市保育園連盟・事務局 |
| 〒860-0004 熊本市中央区新町2丁目4-27 熊本市健康センター新町分室 2階 |
| 電話番号:096-322-0096 FAX番号:096-322-0273 |
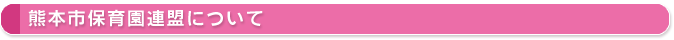 
|
Copyright © KUMAMOTOSHI HOIKUEN All right reserved.
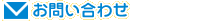 |
| 一般社団法人 熊本市保育園連盟・事務局 |
| 〒860-0004 熊本市中央区新町2丁目4-27 熊本市健康センター新町分室 2階 |
| 電話番号:096-322-0096 FAX番号:096-322-0273 |